|
0 Comments
ゲームデザインに関係する文化の相違、東京のインディーゲームコミュニティ、ゲームパフォーマンスを最適化するための技術について話します
シュールズ・ダグラス (Douglas SCHULES)によるインタビュー
Daedalus Machine Phantom Islandについてお聞きしたいと思います。簡単にサークルについて背景やこれまでの歴史を教えてください。 Phantom Island 私が専門学生の時に一緒にゲーム開発をしていたチームがベースとなり、「会社では作れないゲームを作ろう」という意思の元2016年の2月ごろにPhantomIslandを立ち上げました。 それからは様々なゲームを考案してはボツにしつつ、現在開発中の「Faye/Sleepwalker」のゲームコンセプトを決め、プロトタイプ版の開発を始め現在本開発を進めている状態です。 立ち上げ当初は人数は4人だったのですが、今は7人で開発を行なっています。 Daedalus Machine サークルとしてこれまでで一番難しかった事は何でしょうか。 Phantom Island 主に人間関係ですね。 特に面と向かって「俺はこのサークルにいらないんじゃないか」と言われたこともあります。今では失敗談として話すことが出来ますが、その時期は集まってくれたメンバーを不幸にした上、開発もできなくなるのではないかというストレスとプレッシャーでご飯が喉を通らなくなるほど苦しかったです。 Daedalus Machine この回答はあまり聞かないのですが、人間関係はゲーム開発において大切です。同じような問題に直面しているデベロッパーのためにかせ様の経験を少しだけ共有いただく事は可能でしょうか。 Phantom Island 開発を始めた当初は「リソースの多さを補ってもらうための人員」として多人数での開発を行っていました。こういった考えで開発をしている他の方も、もしかしたらいるかもしれませんがこれは誤りでした。 自分に裁量を全て集め、他のメンバーは言われることをただこなすだけという形になってしまい、メンバー個人を作業者としてしか見ていなかったためです。個人としてはそう思ってはいなかったのですが、そう受け取られてしまったので結果は変わりません。 また、プロトタイプから本開発に移行する際すべてのソースコードを破棄したのですが、これによって他のメンバーの成果物まで許可なしで消したことで反感を買いました。 総合的に見て、「自分はチームの一員としてゲームの開発をしている、自分の考えがゲームに反映されている」という感覚を損なってしまった、メンバー個人に対しての誠実さが足りなかったことが問題だと思っています。現在は、今まで私が決めていたゲームの細かいデザインや、ソースコードの設計などは担当のメンバーが責任を持って決めてもらいつつ、私は大まかな確認をする方針を取っています。 具体的な例では敵の挙動やバトルデザインなどはほぼ全てを担当するメンバーに任せています(もちろん、話し合いはします)。 もう一つ、他人の成果物を尊重することを必ず意識するようにしています。自分のものではなく他の人と一緒に作り上げているものだと考えるようになりました。 Daedalus Machine 現在のプロジェクトは「Faye/Sleepwalker」と呼ばれる3Dのアクションゲームです。これまでどのくらいの製作期間がかかっていますか。 Phantom Island 2016年8月からプロトタイプ版の開発を始めたため、2018年10月現在ですと2年2ヶ月かかっている計算になります。ゲームコンセプトの設計などから考慮すれば、2年5ヶ月ほどになると思います。 Daedalus Machine このゲームのコンセプトを少し教えてください。 Phantom Island 「目が追いつかないほどの速さ」をベースとして、ゲーム性に関連する「直感的なアクション」とシナリオに関連する「人としての成長」を乗せています。 「目が追いつかないほどの速さ」というのは、私が新幹線に乗っている時に景色がどんどん移り変わっていくのを見て思いついたのですが、人は視界に入って来るオブジェクトがめまぐるしく変わるとそれを脳で処理しようとします。 ではそもそも処理が追いつかないほどの視界の切り替わりが起きた際にどうなるのかというと、混乱を引き起こします。 しかし、混乱を引き起こすか引き起こさないか・・・というギリギリの状態は、脳が常に情報を処理し続けるので一種のカタルシスを引き起こします。それを戦闘やオープンワールドの移動という点で表現しようと思ったのでベースのコンセプトに据えました。 Daedalus Machine おっしゃるとおり、スピードや勘がゲームメカニズムというのが分かります。ゲームデザインやゲームのストーリーでそういったアイデアがどう反映されているか詳しく教えていただけますか。 Phantom Island ストーリーはあまりコンセプトに関係してこないのですが、ゲームデザインについてはまず「広い世界を小さく感じさせるほどの高速移動」を実装しています。飛行や高速な地上ダッシュ、いうなれば「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のような高速移動です。 これはコンセプトの達成以外にも移動にかかる時間も減るため、オープンワールドゲームに求められるフィールドの密度、物量を相対的に減らすことができるのではないか・・・と思っています。 Daedalus Machine 技術的な面から言ってゲームの中に「スピード」というコンセプトを実現させるのはどれぐらい難しかったですか。また、どうやって実現させましたか。 Phantom Island 技術的な面で言うと、プレイヤーキャラクターや敵キャラクターの挙動が早いため壁などのコリジョン抜けが多発してしまい非常に悩まされました。また、プレイヤー、敵キャラクター共に「ワープして攻撃を行う」ような状態があるのですがコリジョンの中に埋まらないように位置の計算を行うのが非常に面倒な作業でした。 コリジョン抜けに関しては1F前の位置と次に移動予定の位置の間にコリジョンがあるかどうかを検索し、障害物がある場合は戻る基本的な実装を行っています。ワープのコリジョン抜けに関しては、ワープ予定位置がコリジョンと重なるかどうかを事前に計算しておき、重なる場合は予定位置の上部or下部に位置をズラすなどの対応を行なっています。 Daedalus Machine 現時点でこのゲームはデモですが、いつ頃完成版ができる予定ですか。 Phantom Island 当初は2018年冬に発売の予定でしたが事情により延期になりました。 2019年の春にDL版の発売を、2019年の夏にパッケージ版の発売とSteam版のリリースを予定しています。 Daedalus Machine ゲームの主人公は女性です。アメリカではあまり見ない(増えてきてはいますが)のですが、日本では特にインディーゲームや同人ゲームで結構ありますよね。どうしてだと思いますか。 Phantom Island 欧米と日本の文化圏の違いは一度考えるべきかと思いますが、日本に限った話をすると「感応、共感に関する能力」というのは往々にして好まれる傾向にあるかと思っています。 男性より女性の方がコミュニティを作成し、継続する力が高いと言われており、僕自身もそういう実感はあります。 また転じて「女性は他人を理解し、支えることができる。あるいはそれをするべき」という認識もまたあるのかなと感じています。これは各々の感覚によって異なると思いますが。つまるところフレンドリー、最初から精神的距離が近くても良い、多人数に受け入れられやすい。そういった認識の土壌があり女性のキャラクター、女性の身体的特徴を持ったキャラクターとして生まれるのかと思っています。男性キャラクターに対して女性キャラクター、ないし女性的特徴を持ったキャラクターの方がプレイする際の心理的障壁が少ないことを私自身も感じています。 これはあくまで持論ですし、女の子の方がKAWAIIよね!というハイコンテクストな印象で女の子にしている人が多数だと思います。KAWAIIはアヴリル・ラヴィーンを筆頭に、ティーンに向けて欧米に持ち込まれる前には存在しなかった文化でもありますので、そこも差異になっているかなと思います。 Daedalus Machine この「差異」についてもう少し詳しく教えていただけますか。 Phantom Island KAWAIIというハイコンテクストな話で言えば、「色彩感覚」が例にあるかと思います。 視覚から得られる色彩情報は日本人と欧米人で明確な差異がありますので。ビビッドカラーなどはムキムキのお兄さんに合わせることはほとんどなく、女の子に合わせることが多いかと。 Daedalus Machine かせ様のかんがえではこの「KAWAII」はある程度はマーケティング戦略だと思いますか。 Phantom Island まず間違いなくマーケティングの戦略になり得ると思っています。 今作では大きくはやれませんが、今後はそういったキャッチーな要素も積極的に取り入れていきたいと思っています。 Daedalus Machine プレーヤーにはこのゲームでどんな体験をしてほしいと思っていますか。 Phantom Island 「訳が分からなくなるけどなんか楽しい」をまず体験して欲しいと思います。 その先に離れられなくなるようなカタルシスが待っていますので。私達はそれが体験するためのサポートができるよう、システムを実装しています。 Daedalus Machine ゲームプレイの観点から、ノーマルモードとスリープウォーカーモードはゴッドオブウォーや無双ゲームのようなアクションゲームと似ている所があると思います。これらから影響を受けましたか、また他のゲームから影響を受けていればどのゲームだったか教えてください。 Phantom Island ゲームのコンセプト設計の際に参考にしたか否かという部分で言えば、答えはNOです。今までの「受け入れられたアクションの方程式」の参考にしたという点では答えはYESです。 こういった敵を爽快に倒していくアクションゲームはスラッシャーゲームと私は呼んでいますが「God of War 3」、「Devil May Cry」、「NieR」、「Kingdom Hearts」、「Bayonetta」などが一番に思い出されるので、これらにはアクションの手触りという点で影響を受けていると思います。 特に「NieR Automata」のアクションは手触りがよく、近年で一番出来が良いと断言できます。全てのアクションゲーム開発者はプレイをするべきだと思います。 余談ですが、「Faye/Sleepwalker」では敵の攻撃に合わせて回避をすると、スローモーションエフェクト + 白黒の画面効果が出るようになっていますが、これは「Bayonetta」のウィッチタイムの影響ではなく偶然被ってしまったということを主張しておきます(笑) Daedalus Machine インタビューの最初に会社では作れないゲームを作りたかったとおっしゃっていますが、どんなゲームを作りたかったか、についてもう少し詳しく教えていただけますか。 Phantom Island まず、日本の中小会社でかつ現在の私がゲームデザインを行える会社は存在しないと思っています。ゲームの売り上げの見通しが、開発費以上に立つかどうかという点 + まだまだ業界の中では若手なのでプロジェクトを任せてもらうというのは難しいためですね。 なので売り上げを度外視し、ゲームデザインに挑戦していくためには社外でやるしかないと思った次第です。 Daedalus Machine ゲームコンテンツというより、産業の構成についてお話しくださっていますが、個人のクリエーターはチームによって速く利益をあげられる必要があるという現在の産業の環境ではあまりそういったポジションがないとお考えという理解でよろしいでしょうか。「ウルティマ」や「ウィザードリィ」のように最初から最後まで個人でデザインできていたPCゲーミングの時代を懐かしく感じておられるように見受けられますが、モバゲー市場ではある程度その時のような感じと言えないでしょうか。 Phantom Island より詳しく言えば私が好むゲームデザインはシンプル、感覚的、刹那的なものが多いのですが、ゲーム業界ではよりリッチで長く遊べる、様々な遊びを複合させたゲームデザインが求められていたように感じました。 そういった指向性の違いを感じたという話になります。またモバイルやコンシューマに限らず、ポジション自体は存在すると思っていますが、それは全体のゲームデザインではなく細かく分割された一部の遊びのデザインを担当するような形になると思います。モバイルゲーム市場では数年前はまさにそうだったかもしれませんが、今はコンシューマの後追いをしているような印象です。 PCゲーミング時代を懐かしく感じている、といっても私はまだ24歳なので当時を知りませんが、その時代を現役で体験された方と同じような経験を積まないといけないかなと思ってはいます。 Daedalus Machine ゲームのデザインについてですが、このゲームはUnityで作られていますね。このゲームを作る前にどれくらいUnityを使った経験がありましたか。 Phantom Island 「Faye/Sleepwalker」を開発する前はUnityは1年ほど使用していました。 その頃はOculus Rift DK2がバッカー向けにリリースされた時だったのですが、VR対応のマルチプレイシューティングゲームをUnity 5で開発していました。 そのゲームは日の目を見ることなくHDDの奥で眠っていますが・・・ Daedalus Machine VRゲームを作ろうとされた方にお話しを伺った事はあまりないのですが、他のゲームと比べてVR用のゲームというのはデザインや計画でどんな違いがありますか。 Phantom Island ゲームデザイン的な面でいうと、普通のゲームより視界の占める範囲が圧倒的に大きいため視覚的なフィードバックを重視する必要があります。また、ノウハウが溜まっていない分野のため試行錯誤するプロセスが必ず必要になるので開発時間は多くとる必要があります。 そして一番大事なことですが、酔い止め薬を完備しないと人が倒れます(笑)。 開発初期のテストプレイはまだゲーム的に洗練されていない分、耐えられないほどの酔いがあるので・・・私も毎日酔っては気持ち悪くなっていました。 Daedalus Machine Faye/Sleepwalkerを開発されるにあたって、ゲームプレイの動作が思ったようにいかないなど、思わぬ後退や遅れを経験されたかと思いますが、どういった経験があったか例を挙げて教えていただけますか。またそれを解決するために何をしたか教えてください。 Phantom Island アクションの手触りという部分で
「攻撃をしているのに当てても気持ちよくない」はサウンドや画面効果、モーション遷移といった点が問題と考えました。コンセプト設計を踏まえ、プレイヤーに思考の暇を与えるヒットストップなどは導入しない方針だったのですが、小さなヒットストップは導入することにしました。それなりに改善はされているのですが、まだまだブラッシュアップ途中というところです。 「攻撃を食らうと不快な気持ちになる」は前向きな感情であればむしろゲームへのめり込むきっかけとなるので良いのですが、これは「理不尽」という部分が不快さの原因でした。 理不尽さを感じる原因としてはずさんなカメラワークや、早すぎる敵の攻撃判定の発生、プレイヤーのコントロールに起因すると分析し、全て改善しました。今後も新規実装される敵は「理不尽でないか?」を元に調整を行うと思います。 「ずっとプレイしていられない、飽きる」は単にプレイにメリハリがないことが原因と分析し、画面効果の充実やバレットタイムのような演出を入れるようにしました。この点では映画「The Matrix」を参考にしています。映画の演出はゲームと相性が良く非常に参考になります。 Daedalus Machine なるほど。これらの技術的に細かな点というのはうまくできたらゲームがより洗練されてくると思います。ずさんなカメラワークについて特に面白いと思いますが、理想的なカメラワークとはどのように動くのが良いと思いますか。また、Fayeのどういった所に不満を感じましたか。 Phantom Island 理想的なカメラワークに求めるものは究極的には一つで「見たいものが見たいときに見られる」ことです。なので、ユーザーがこのプレイケースではどこに視点が欲しいか、どれくらいの視界の広さが欲しいか、カメラシェイクなどの演出はどの程度までなら許容できるかを全て洗い出す必要があります。 特に3Dの視界を自由に動かせるゲームは360度カメラを回転出来るため、ある程度ユーザーに操作権限を与えつつ、違和感のない範囲で視界を誘導していくというシステムが必要であると思っています。 当初はカメラワークが敵と自分を映して、それ以外はユーザーが見たい場所を自分で操作して見るのみでしたので、操作量も多かったです。見たい場所を見たいと思ったときに、ユーザーが操作する必要があるというのはそれだけでストレスですので・・・。 Daedalus Machine 「敵と自分を映して」というのはどういう意味でしょうか。 Phantom Island 説明が不足していましたが、バトルを行なっている際のカメラワークとして敵キャラクターとプレイヤーキャラクターを自動的に画面内に収めるように、カメラ位置を固定するような仕組みを取り入れていました。バトル外ではプレイヤーがカメラを操作するのみで、今は実装されている、場所に対しての注目機能などが存在しなかったということです。 Daedalus Machine 実際にどんな事をして問題を解決されましたか。 Phantom Island 「Faye/Sleepwalker」では、ユーザーの操作を奪うカメラの強制移動はストーリーやフィールドギミックの演出時のみで、それ以外は全てユーザーが操作することが可能になっています。 ゲーム的に注目してほしい場所を視界内に収める際は視界を意図的に広く、かつ注目する場所とプレイヤーキャラクターの中間点を映すシステムを実装してあります。これによって「あそこに行けば何かありそう」と意識付けられるため、ユーザーの行動もある程度誘導できるようになりました。 Daedalus Machine これに関して、デザインで最も難しい問題はどんなものがありましたか。 Phantom Island 3Dグラフィックスのクオリティと、ゲームパフォーマンスの両立がとても難しい問題としてありました。特にオープンワールドですので、パフォーマンスには常に気を使わなければあっという間に60fpsを切ってしまいます。 Daedalus Machine どう解決されましたか。 Phantom Island パフォーマンスに関してはLevel Of Detailと、一部ではImposterという仕組みを実装しています。また、Unityに実装されているGPU Instancingという仕組みを利用して描画を最適化しています。 クオリティ面での妥協はしませんでした。 Daedalus Machine ImposerというのはUnityのImposerシステムの事でしょうか。あまりよく知らないのですが、3Dアセットを2Dに変える事によってパフォーマンスを上げるのでしょうか。 Phantom Island Unityには実装されていないため、独自実装をしました。Unreal Engine 4には最近実装されたようです。「Fortnite」で取り入れた手法のようでした。 3Dアセットを2Dアセットに変えるという認識で概ね間違いありません。 Daedalus Machine それがどう動くのか少し教えていただけますか。どんな事をして実装されましたか。 Phantom Island ある程度端折った話をすると、カメラから見た3Dオブジェクトの見た目を動的にテクスチャに対して書き込みます。そのテクスチャを3Dオブジェクトの代わりに表示することで、見た目は3Dオブジェクトとほぼ同様、かつコストの低い描画を行うことができます。 カメラは移動するので、その都度テクスチャの更新が必要になりますが、更新頻度はパフォーマンスのネックになりうるので調整が必要です。 また、テクスチャに対してライティングを適用したオブジェクトの見た目を書き込む計算は非常に面倒でコストが高いので、ライティングがなくとも見た目的に違和感のないオブジェクトのみに適用しています。 Daedalus Machine いずれにせよ、グラフィックスのレンダリングのために多くのリソースを使ったように見えます。パフォーマンスを上げるために他にされた事はありますか。 Phantom Island カメラのレンダリングパスを途中からDeferredに変更した上で、全てのShaderを修正しました。昼夜の時間経過があるため動的光源しか使えず、更にポイントライトのみでディティールを上げる必要があったためです。 「ゼルダの伝説 BotW」ではライトマップを時間経過で更新する手法を取っていたようなので、そちらも検討しましたが技術的に挑戦する時間がなかったため見送りました。 Daedalus Machine かせ様がされたこれらの事を元にどれくらいパフォーマンスは上がったとお考えでしょうか。 Phantom Island 解像度1280 * 720 で40fps程度しか出ていなかった開発初期と比べ、解像度1920 * 1080で60fpsが安定して出るようになったのでかなり良くなったのではないかと思っています。 Daedalus Machine グラフィックや音楽のアセットはご自分でデザインされましたか? Phantom Island 3Dグラフィックスに関してはアセットを購入し、Blenderなどで改造した上で使用しています。 サウンドは自分で作ったものもあればアセットで購入したものもありますが、ゲームにマッチしていないので最終的には全て外注し差し替える予定です。 Daedalus Machine 少し戻って、Phantom Islandのメンバーについてお聞かせください。グループは現在7名の方がいらっしゃるとおっしゃっていましたがグラフィックスや音楽アセットのデザインができる方はいらっしゃらないようにお見受けします。メンバーの方々はそれぞれどんな事をされていらっしゃるのでしょうか。 Phantom Island 敵全般のバトルデザイン + プログラム担当の方が1人 UIデザインの方が2人 UIプログラム担当の方が1人 エフェクトデザイン担当の方が1人 レベルデザイン担当の方が1人 それ以外は現状私ですが、それぞれ担当の垣根を越えて色々意見を出し合ったりしています。 Daedalus Machine このゲームは日本語版と英語版がありますが、翻訳はご自身でされましたか、それともPlayismなどのサービスを使われましたか。 Phantom Island サークルのメンバーの一人が、プロの翻訳者と友人ということで無償で行なっていただきました。今後の対応言語は日本語、英語、中国語、フランス語を予定しています。 Daedalus Machine それはとても野心的ですね。なぜこれらの言語をお選びになったのでしょうか。 Phantom Island 日本語は母国語なので、それ以外はSteamの上位ユーザー数から英語と中国語を選択しました。フランス語は、東京ゲームショウに出展した際に欧州の方に受けが良かったので選択しました。 これについてはもう少し精査する予定です。 Daedalus Machine どのようにローカリゼーションをされる予定ですか。どのようにゲームに取り込まれる予定でしょうか。 Phantom Island ローカライズの発注方法については多分に漏れずExcelでテキストを書き換えてもらっています。テキスト以外の部分でいうと、ボイスなどがあると思いますがボイスに関しては日本語のみになる予定です。 既にゲームには日本語と英語が実装されており、12月に中国語(繁体字)が実装される予定です(2018年度)。 Daedalus Machine インディゲーム界についてですが、東京でインディデベロッパーとして活動することについてどう感じていらっしゃいますか。 Phantom Island 東京はイベントが豊富で、「同人ゲーム」をベースにしたコミュニティも多いため情報収集やデビューにはちょうどいい環境だと思っています。 しかしインディデベロッパーとしてステップアップしたいのであれば東京、国内ではやはり難しく、資金が底をつく可能性が高いと思っています。それは「同人ゲーム」というコミュニティ外に活動の範囲を広げることになるからです。 「同人ゲーム」は国内(最近はそうでもありませんが)かつ、ファン活動や趣味での活動が主だと思っています。それ以外で成功を収めたいなら国外を視野に見据えなければいけないと感じています。 どこかから資金提供などがない限りは、国外向けにパブリッシングを行ってもらえる企業を探すか、会社を立ち上げ取引をする方が長く活動はできるのかなと。 Daedalus Machine 日本国内で同人ゲームを開発するには資金が大切だとの事ですが、たいていのグループは個人で資金を出されていると理解しております。かせ様のご経験ではこの理解は正しいでしょうか。 Phantom Island 私自身も「同人ゲーム」の開発は個人資金で手弁当でやってらっしゃる方が多いと思います。 「同人ゲーム」に大切なのは資金よりも「自分のやりたいことを楽しくやる」というようなマインドだと思っています。これは決して非難ではありませんが、イベントで体験版を出し続けて数年、完成はまだしていないけど楽しい!という方もいらっしゃいます。 個人が楽しむという点でとても良いことだと思います。 その上で私が資金が大切というのは「野心があり、成功を収めたいインディデベロッパー」に対してですね。 こういった議論は何度も行われ、その度コミュニティが疲弊していくのであまり話したくはない内容ですが個人的に「同人」と「インディー」で差異がある事が多いなと感じたことは「成功を収めるという野心があるか否か」という部分になります。 Daedalus Machine なぜこのような状況だと思いますか。なぜ海外で行われているキックスターターや他のクラウドソーシングのような方法が使われていないのでしょうか。 Phantom Island 一言で表すことはとても難しいと思いますが、キックスターターなどのクラウドファンディングはむしろ行われているほうだと思います。問題はクラウドファンディングという手法がユーザー側に根付いておらず、お金を直接クリエイターに無形の支援として贈る文化に理解がないことだと思っています。 最近はYoutuberの台頭による投げ銭文化によって徐々に広まりつつありますが、昔はクリエイターに対しては成果物にお金を払うのがユーザーだ、という方が多かったと認識しています。 Daedalus Machine 新しく活動を始めたデベロッパーのために、どんなサポートがありますか。 Phantom Island 「新しく活動を始めた無名かつ個人のデベロッパー」に対しての政府からといった公的なサポートは一切ないと言っても過言ではありませんが、コミュニティは暖かく迎え入れてくれると思います。 特に「Tokyo Indies」はお勧めできるコミュニティですので、一度行ってみると良いかと思います。 Daedalus Machine Tokyo Indiesが面白いのは国内外のデベロッパーが一緒に行くという事です。どれくらい国内のデベロッパーと国外のデベロッパーが交流したり、アイデアや意見交換していると思いますか。 Phantom Island 日本国内では、コンスタントに開催されているコミュニティで唯一の国際交流の場といってもよいと思います。 人種で区別するのはナンセンスですが、日本人ではない方の声を聴ける上、交流ができるというのは素晴らしいことです。何度か参加させてもらいましたが、意見交換などはかなり活発です。何度も言いますが、日本でこう言ったオープンなコミュニティは「Tokyo Indies」が唯一であると思います。 Daedalus Machine 東京ゲームショーに参加されていますが、どうでしたか。 Phantom Island 他のイベントと違い、一般参加者の数が段違いに多いです。 ゲーム業界で仕事をされている方も来場されていたため、厳しい意見もいただきましたが参加してよかったと思います。 Daedalus Machine 東京ゲームショーへの参加の仕方を教えてください。 Phantom Island 夏の前ごろにインディーブースの出展者募集の告知が出ますので、公式サイトから応募を行います。 応募の際は展示形式が2種類あり、選考によって採択される誰でも応募ができるタイプAブース(10万円ほど)、法人専用のタイプBブース(20万円ほど)から選択します。この出展料はインディーブースにスポンサーが付くかどうかで価格が変動し、スポンサーがいる場合は基本的にタイプAブースは無料になります。 今回の出展ではタイプAブースに応募し、採択されたため出展料は無料になりました。応募の際は完成度やゲーム概要などが聞かれ、開催年によってはデモビルドの提出が必要になります。 応募数は例年300件ほどで、その中から採択されるのは50 〜 100未満ほどの様子です。 Daedalus Machine 他のイベントに参加された事はありますか、また参加される予定はありますか。 Phantom Island 「デジゲー博」「Megabit Convention」「コミックマーケット」「ぜんため」などのイベントに参加させていただきました。 今年(2018)は11月に「デジゲー博」への出展を予定しております。 来年は台北で行われる「Taipei Game Show」への出展と、夏に「コミックマーケット」で完成版のパッケージ版の販売を行う予定になっています。 ほかのインディーデベロッパーとのインタビュー
8/5/2018 0 Comments 秋空シンセシス:日本のインディデベロッパーとのインタビュー |
|
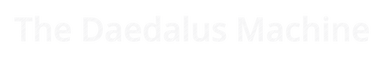

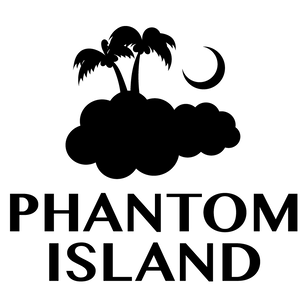



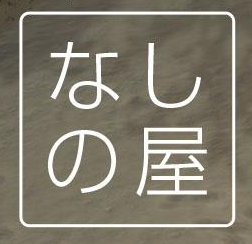
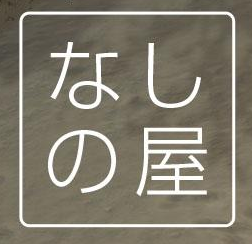



 RSS Feed
RSS Feed