|
12/14/2017 0 Comments Reminisce: 日本のインディデベロッパーとインタビュー
最新作、インディデベロッパーによるマーケティングの難しさ、TGSについて
Reminisceとのインタビュー
シュールズ・ダグラス (Douglas SCHULES)によるインタビュー
Read the interview in English
Daedalus Machine
C92で「Link: The Unleashed Nexus」の体験版を入手しましたが、Steamで完成版が買えるのに気が付きました。C92版とSteam版の違いは何ですか。 Reminisce 現在Steamで販売しているものは、私の処女作となる作品です。2017年に入り、「Link: The Unleashed Nexus」のPlaystation 4でのリリースが決定しました。そこで、折角なのでゲーム自体を1から作り直してしまおうということで「Restructured Heaven」という副題をつけフルリメイクをしているものがC92版となります。 Daedalus Machine ゲームのストーリーとデザインについて少し教えていただけますか。 Reminisce 基本的には「スピーディで簡潔、しかし応用次第でテクニカルなタイムアタックを楽しめる」というゲームコンセプトです。難易度は高く設定していますが、ゲームオーバーというものを排除しスムーズなリスタートを可能にすることでトライ&エラーを楽しんで欲しい、という思いがあります。じっくり腰を据えて遊ぶという、私が家庭用ゲーム機のソフトに求めるプレイングを目指しました。 ストーリーは、アクションゲームなのでメイン部分は濃くしていません。プレイヤーはアクションを求めていると思うので、まずは深く考えずプレイできるようにしています。バックストーリーが用意されており、ゲームの進行と共にそれらが明らかになります。一通り遊んだ後で、全体の物語について反芻・考察していただくのが理想です。 Daedalus Machine 「タイムアタック」についてなのですが、プレイヤーが各ステージの終わりでランキングが出ます。このランキングはどのようにして決められるのか教えていただけますか。またどうやったら高いランキングを狙えるかヒントを教えてください。 Reminisce 現在はクリア時間によってランクが分けられています。リリース時には別の条件が追加されるかもしれません。また、危機を緊急回避する能力を使わずにクリアすると「S+」のように、ランクに「プラス」表記が追加されます。 高いランクを狙うには、まず攻略してみて自分に合ったルートを探すのがいいでしょう。プレイ動画を上げてくださっている方の中には、私自身予想もつかなかったルートでのタイムアタックに挑戦している方もいてとても嬉しいです。 Daedalus Machine ウェブサイトを見ると同じようなテーマのゲームシリーズがあるように見受けられます。これらのゲームの内容とそれぞれの関係について説明していただけますか。 Reminisce ハイスピードなアクションと「デジタル時代の精神文化」を描く「Link」シリーズと、音楽とのシンクロニティと神性を獲得しようとする精神体たちの闘いを表現した「空棲精神性レゾナンス / コンフリクタ」というゲームを発表しています。 「Link」シリーズについては毎回違った精神的な現象を扱い、継続的に作品を作り続けていきたいです。来年には全く新しい新プロジェクトも予定しています。 Daedalus Machine 全体のテーマについてもう少し詳細を教えていただけますか。どんなタイプの現象を扱う予定ですか、またなぜその現象を扱うことにしたか教えてください。 Reminisce 一貫して「現代において、精神というものがより大きな意味を持った社会」を扱います。都市伝説や精神病など、多くのものが人間の精神から派生しています(Unleashed Nexusのネタバレになるため、具体的な記述は避けます)。 自身が経験した非日常を「Link」の世界観に合わせてリミックスしたものを。精神病などとも少し関わりがあるかもしれません(いや、僕自身は精神病ではないです。大丈夫)。 Daedalus Machine それと、今度の新しいプロジェクトについて教えてください。何かヒントでも構いません。 Reminisce 詳細は固まりきっていないですが、とある少女の人生をフォーカスした作品を考えています。ゲームをプレイしている人間は、その少女にとってどんな存在なのか。そして、共にどんな選択をしていくのか。どんな人生を歩むのか。という答えのない問題を問いかけるゲームになる予定です。ゲームキャラクターとプレイヤーの新しい関係を模索します。 Daedalus Machine 「Link: The Unleashed Nexus」のレベルデザインを見てみると「Metroid Prime」や「DMC: Devil May Cry」のような3Dアクション・アドベンチャーゲームを思い出します。このゲームを制作したときはどんなゲームの影響がありましたか。 Reminisce 具体的にどんなゲームに影響されたというわけではなく、ゲームの構造はとにかく自分の好みや理想を反映していると思います。どれだけ理想に近づけるかはまだ分かりませんが……。 レベルデザインに関しては、ほぼ自分が寝ているときに見る「夢」から着想を得ています。繰り返しテストプレイをしているので、ついに夢でも飛べるようになりました……。 Daedalus Machine 一般的に、どんなゲームが倉澤様に影響を与えましたか。 Reminisce アクションゲームを幼少の頃から遊んでいたので、作ってて一番テンションが上がるのがアクション要素ですね。初めて自分の家で遊んだゲーム機はドリームキャストでした。特にゲームがうまいというわけではないですが、アクションが上達していく快感、難所を突破した爽快感、脳が追いつかなくても反射的に高速で敵を捌いていく感覚の気持ちよさが大好きで、それを自分のゲームでも感じていただけたら最高です。 Daedalus Machine どのゲームが好きでしたか。またその理由も教えてください。 Reminisce 僕自身のゲームの原体験といえば、ゲーム機「ドリームキャスト」で遊んだ内容がとても大きいです。3Dになった「ソニック」シリーズや、一本のストーリーを元にフリーローミングを楽しめる「シェンムー」、ハックアンドスラッシュの醍醐味が楽しめる「ファンタシースターオンライン」等です。 ゲームを作っていく上で糧となっているのが、「ダライアス」や「東方プロジェクト」などのアーケードタイプのシューティングゲームです。ストーリーが希薄になりがちなSTGというジャンルで、凝った演出をしているのに痺れます。特に個人製作の「Hellsinker.」というゲームはカッコイイ演出の塊で、ずっと僕のバイブルになっています。 Daedalus Machine 御サークルについて詳細を教えていただけますか。例えば、どのぐらいの期間、またメンバーの人数とそれぞれの役割、これからの活動、など。 Reminisce 2014年から活動を開始し、2016年までの製作ではもう一人のメンバーがエフェクト、テクスチャ、材質設定などを担当していました。2017年に入ってからは彼が多忙のため、私一人でほぼすべての製作をしています。スカイスフィア(3Dゲーム内の、空にあたるデータ)と効果音は購入したアセットを使用していますが、それ以外のプログラム、企画、3Dモデル、アニメーション、エフェクト、マテリアル、楽曲等は自前のものになります。 Daedalus Machine それはたくさんの役割を担っていらっしゃいますね。3Dモデルのデザイン、アニメーション、スコアなど、どのプログラムを使っていらっしゃいますか。 Reminisce 3Dモデルとアニメーションは「Blender」を、楽曲の製作は「Reaper」というDAWを使っています。テクスチャは「Substance Painter」で描いています。そうした素材をUnreal Engine内で統合し、作品を作り上げていきます。 Daedalus Machine 倉澤様の経歴を教えていただけますか。なぜゲームクリエーターになろうと思ったのですか。 Reminisce 私はほんの数年前まではしがない文系学生でした。将来についてぼんやりと考えたまま就活の時期になってしまい、そこで偶然触ったのがゲーム開発用ミドルウェア、「Unreal Engine」だったのです。リッチなシェーディング表現、比較的簡潔なスクリプト、次世代のレベルエディタに惚れ込み、何の根拠もなしにゲームを作って生きていくのだ、と決心しました。 特にUnreal Engine 4の「ブループリント」というビジュアル化されたプログラムは革新的で、面白いようにプログラミングを進めることができました。自分の製作スタイルとぴったりハマったのだと思います。そうして3ヶ月ほどで完成したのが「Link: The Unleashed Nexus」の最初のバージョンでした。ゲームの製作に合わせて必要な技術を独学で学んでいき、現在の開発につながっています。 Daedalus Machine 独学で学ばれたとのことですが、Unreal Engineを使われてどのような事が一番難しかったですか。 Reminisce あまり難しかったことを意識はしていないです。強いて言うなら、プログラムやコンピュータ、ソフトウェアに関する知識が薄いため、原因の分からないエラーが出たときの解決に時間がかかってしまうことでしょうか。 Daedalus Machine 以前に比べてより多くのデベロッパーがゲームを作成するのにUnreal EngineやUnityを使っていると聞きます。日本のデベロッパーはなぜゲームを作るのにこういったツールを使うことが増えてきたと思いますか。 Reminisce プログラムの基礎的なメカニクスを学んでフルスクラッチで作るより、ゲームエンジンを使用することでその過程を飛ばせるのがとても大きいです。特に個人や小規模での製作ではそのメリットが顕著になると思います。プログラマーが不在でも、デザイナーがゲームのシステムを作ることが可能になりました。 Daedalus Machine TGSで少しお話しましたが、日本のインディデベロッパーにとってゲームのマーケティングや配信において助けを借りる事は重要です。現在、Reminisce様は一番効果的な方法でそういう活動を果たそうとお考えになっているとの事ですので、お考えをお聞かせいただきたいと思います。日本のインディデベロッパーは、特に海外でプロモーションする時、どんな選択やサポートがありますか。 Reminisce 個人で開発はできても、個人でのプロモーションは難しいです。いくらSteamなどの大きな配信媒体でゲームを販売しても、宣伝効果がなければ結果はついてきません。セルフパブリッシングをした結果、その厳しさは実感しました。1人でできるプロモーション努力はありますが、それでは不十分です。ローカライズやアドバタイズに関しては素直にパブリッシャーと協力して行うのが最善だと思います。 Daedalus Machine アメリカでは多くのインディデベロッパーが自分の作ったゲームをTwitterなどのソーシャルメディアを使って宣伝しているのを見ますが、そういった努力がはたしてうまくいっているのか分かりません。「セルフパブリッシング」を試みたとのことですが、実際どのような方法を試されましたか。また日本のマーケットではどうするのが効果的でしょうか。 Reminisce セルフパブリッシングをした経緯としては、最初にパブリッシャーにSteamへの販売を代行していただく予定だったのがキャンセルされてしまい、自力で出さざるを得なくなったという理由があります。Steamのコミュニティにより販売するゲームが決定される「Greenlight」システムを通過し、Steamとのやり取りを経て販売まで漕ぎ着けました。 Steamタイトルに与えられている宣伝方法等を試し、中規模セール時には一定の効果があることは確認しています。 日本のマーケットにおいて、個人・少人数製作のゲームはあまり露出機会がなかったように思います。少なくともPCゲームにおいて、ダウンロード販売プラットフォーム内で全年齢向けゲームが注目を集めるのはかなり難易度が高いです。 「Link」はコンシューマゲーム機向けに「Play, Doujin!」プロジェクトの力をお借りしてリリース予定です。まずPlayStation 4向けに開発し、その後他のゲーム機についても考えています。インディーゲームにとって、レッドオーシャンと化しつつあるPCゲーム市場よりはコンシューマゲーム機のほうが可能性を感じられるのかな、と思います。 Daedalus Machine ゲームのローカライズについてはパブリッシャーと協力する事が重要とのことですが、日本のインディデベロッパーは海外の市場にどれだけ売り出す必要があると思いますか。 Reminisce 日本のいわゆる同人ゲーム文化は、あまり海外を意識していないようにも思えます。ただそれを無理に新しい市場に持っていく必要もなく、製作者自身が必要と感じたら行動すればいいのではないでしょうか。現状海外から日本に入ってくるインディーゲームはあっても、その逆はあまり活発でないように思えるので、その辺の土壌が変わってくればまた変化があるかもしれません。 Daedalus Machine もしあれば、ですが、海外の市場に売り出す事はどのくらいゲーム作成や内容に影響を及ぼしていますか。 Reminisce ゲーム内容では、特に海外を意識しているということはありません。インディーゲームにおいて、プレイヤー層を意識してゲームの根幹を変えようとは思っていません。無国籍で、文化にとらわれないゲームを作りたいです。表現したいものをひたすら盛り込んでいるだけですし、インディーゲームはそうあるべきだと思っています。 Daedalus Machine アメリカと日本のインディデベロッパーでゲームの制作法に違いがあるというお話もしました。例えば、アメリカではゲーム制作をするための募金サイト、「Kickstarter」というクラウドファンディングサイトが幅広く使われるといった人気の方法がありますが、日本ではそういった方法を聞いた事がありません。どうしてだと思いますか。 Reminisce 海外と日本でのクラウドファンディングのあり方の違いだと考えています。私の中では、日本ではあまり未完成の作品に対する投資というものが根付いていないという印象です。サイトによっては、クラウドファンディングを謳っておきながら、ただの予約販売と化しているケースも少なくありません。「Kickstarter」が先日日本でも開始されましたが、日本のゲーム開発者への特効薬になるのは難しいと思います。 Daedalus Machine 日本のインディデベロッパーのためのゲーム制作に必要な資源を手に入れる最も一般的な方法は何だと思いますか。 Reminisce 決定的な手段はなく、非常に難しいです。身を切って開発し、その結果に賭けるケースが多く、インディーデベロッパーが増えない大きな原因となっていると思います。カナダや韓国などのようにゲーム開発に対する政府からの支援があれば……と少しだけ期待しています。 Daedalus Machine 先ほど申し上げましたが、Reminisce様の参加されていたイベントはコミケまたはTGSです。両方のイベントでの経験について教えていただけますか。 Reminisce コミックマーケットでは、展示部分が貧弱なぶん事前に情報を集めて来ている方が多い印象です。午前中に目的のものを手に入れたあと、掘り出し物を探す方が多いと思います。 TGSではインディーゲームコーナーという出展形式なこともあり、知らないゲームを探している方が多いと思いました。勿論事前に気になったゲームだから遊びに来た、という方も多く、ありがたいことにReminisceの作品を目当てに幕張メッセまで来たという方もいらっしゃいました。 Daedalus Machine コミケとTGSに参加するための申し込み手続きの仕方を教えてください。 Reminisce コミックマーケットの場合は事前に申込用紙を購入し、郵送またはWebにて申し込みます。毎回出展希望サークルが多いため抽選という形になること、申込期間がかなりシビアなことに注意が必要です。 TGSのインディーゲームコーナーにおいてはふたつの出展方法があり、片方は作品を動画の形式で応募し、選考で選ばれれば出展できる、というものです。もう片方の方法は出展料を支払い確保する形です。 Daedalus Machine 両方のイベントに参加されて、日本インディゲーム界の将来についてどう思われますか。 Reminisce コミックマーケットとTGSではだいぶ気色が違うのですが、それ以外にもTokyo Indie Fest、デジゲー博などのイベントがあり、インディーゲーム露出の機会は確実に増えてきたと感じています。関東ゲーム製作部、関西ゲーム製作部、Kawazといった地域ごとのゲーム製作コミュニティや、毎月開かれるTokyo Indiesでは自分のゲームを見せ合うこともでき、開発者同士の関わりや展示にも気軽に参加できるようになりました。 課題としては、インディーゲーム界隈でない方々へのアプローチです。「独立ゲーム開発者」という生き方、スタンスが周知され、もう少しメジャーになれば日本のインディーゲームはさらに盛り上がりを見せていくと思います。企業の傾向を見るに、海外でのゲームシーンはより大規模に、強力になり、反面日本では小規模なスマートフォン向けのゲームがメジャーです。そのバランスを変えていくのはインディーゲームだと考えています。 Daedalus Machine ゲームを制作したい方に何かアドバイスがありますか。 Reminisce とにかく行動することです。大小様々な展示会が開かれていて、一年に何度もチャンスがあります。イベントを締め切りとして設定すれば、モチベーションや製作スピードも上がると思います。そこでクリエイターやプレイヤーとの交流をして、次への活力へしていくことで継続的な活動の糧になるのではないでしょうか。ぜひ自分の作品を出していただきたいです。
関連のコンテンツ
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
|
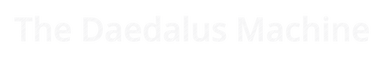

 RSS Feed
RSS Feed