|
現在開発中のゲーム、デベロッパーの背景や開発済のゲーム、サークル名の由来について話します
Hamazaki Factoryとのインタビュー第1部
シュールズ・ダグラス (Douglas SCHULES)によるインタビュー
Daedalus Machine Hamazaki Factoryについて簡単にご説明いただけますか。またこのゲームを作ろうと思った理由を教えてください。 Hamazaki Factory 「Hamazaki Factory」について。 Unityを使ってアプリを完成させた後、GooglePlayにてリリースする際にパブリッシャー名が必要ということで名づけました。ふと思いついた「Factory=工房」という言葉が気に入ったのと、PC雑誌のライター時代のペンネームで使っていた「Hamazaki」という名前を合わせました。そんな感じで、特に深い意味はないです。必要に迫られて適当に作りました。 「Black Blood Breaker」について。 4本ほどスマホ向けのアプリを作ってみて、ある程度Unityの使い方に慣れてきたので、ゲームジャンルとして好きなアクションを作ってみたくて始めました。その制作するにあたって指針としたのは下記の2つです。 1)データは販売されているアセットを頼らせてもらう ゲームで使うモデルや音楽などのデータを自前で用意するのは現実的ではない、ということは明白でしたので、そこはアセット頼りにして、まずは自分ができること、プログラムとデザイン面のみに注力しようと考えました。 2)片手で遊べること・縦持ち横持ちどちらでも遊べるようにする どう作って行こうかとか、本当になにも考えずに、漠然と「スマホなんだから、お手軽に遊べるといいよね。片手で遊べるお手軽さ、あと横持ちだといかにもゲームしてるっぽく見えるから、縦持ちでも遊べるようにしたいね」と思って制作を始めました。ゲームの中身自体も、試行錯誤の末に自分でできる範囲で進めていったらこういう形になったというものです。 まだゲーム作りでわからないことが多いくせに、それなりにちゃんとしたものも作りたいという想いもあってがむしゃらに突き進んできた、という感じですね(そして、なんとなーく見えてきたゴールへ向かって、いまだ突っ走っています)。 Daedalus Machine ゲーム制作についてもう少しお聞かせください。「Black Blood Breaker」に出てくる主人公、ボス、敵はどうやって思いつきましたか。 Hamazaki Factory キャラクターはすべてアセットストアで購入したものであり、自分でデザインしたというものではありません。テクスチャの色や内容を調整したりといったことはやりましたが、基本的には一緒に入っているモデルデータ、アニメーションデータをそのまま使っています。普通のゲーム制作であれば、こういうキャラクターを作りたい、こういうアクションをさせたいから、モデルを作ったりアニメーションを作ったりする流れが自然でしょうが、今回は、こういうキャラがあるから、こういうアニメーションデータがあるから、こんな攻撃にしていこうという具合に進めていきました。 モデルを選んだ基準としては、リアルタッチよりは、少しゲームゲームしたモデルを選びました。モバイルなのでポリゴン数も少なめのモデルで、絵的な統一感のためにテクスチャは手書きテイストのものをチョイスしてあります。なにしろ数を揃えるためには、制作者の違うアセットを利用せざるを得ません。今回ゲームエンジンとしてUnityを使ったのですが、その膨大なアセットストアに助けられました。 Daedalus Machine ゲームデザインについてですが、デジゲー博で「Black Blood Breaker」のレベルデザインについて少しお話させていただきました。ゲームのステージが自動生成(procedural generation)されているかお聞きしたら、固定されているとおっしゃいました。自動生成はリプレイアビリティを増やすと思いますが、開発するのは難しいかと思います。この選択について教えていただけますか。 Hamazaki Factory 「自動生成」というゲームデザインを見送った理由は2つあります。まず自分でそういったタイプのゲームを作ったことがないこと(SFCで初代シレンをそこそこ遊んだくらい)。もう1つが、企画も固めずに日々の思い付きでなんとかゲームという形にするために制作を続けていたものですから、これ以上時間のかかるシステムとゲームスタイルを新たに導入することは「無理」と判断したためです。作ったことはないにしても、自動生成するためには膨大なリソースと快適なゲームプレイをするための調整時間が大量に必要なのは明白でしたから……。その点、ステージ固定にすれば、作った範囲内で色々なものを調整するだけで済むし「まだなんとかなりそう」と思ったのです……それでもすでに制作始めてから1年半以上が経過してますしね。 もちろん、何度でも新しい体験ができる自動生成ダンジョンタイプのゲームが楽しいのは分かっています。とにかく今は、最終的にはそういったシステムを盛り込めたらいいなあと思いつつ、自分のできる範囲でゲームとして楽しい体験ができるようにまとめています。なにしろ世に出さないことには何もならないですからね。 Daedalus Machine 「Black Blood Breaker」は音声が入っていますが、音声を入れるプロセスについて教えてください。 Hamazaki Factory 以前、個人ゲーム制作者の集まりみたいな場所に参加したときにお会いしたフリーで活動されている声優さんに依頼しました。スタジオを使わず自宅で収録可能なこと、会場で会って話した時にちゃんと一緒に仕事ができそうということが決め手となったと記憶しています。わざわざ声を入れたのは、単に「自分のゲームに声を入れてみたいよね」「声が入ってるなんですげーじゃん」という欲求に従っただけです。 Daedalus Machine ゲームを作り始めたきっかけを教えてください。 Hamazaki Factory ゲーム作りを始めた理由は単純明快で、「ゲームを遊びたかったから」です。ゲームを作り始めたのは、8ビットマイコンの時代……というはるか昔のこと(三十年以上前のことかなぁ)。ソフトは売っていましたが高くて買えず。運よく親に買ってもらったPCを使って、雑誌のプログラムを打ち込んだり、ちょっとしたミニゲームを作っていました。そこから雑誌のライターをしながら、雑誌に掲載した言語やライブラリを使ったサンプルゲームを作ったりして、お遊びながらゲーム作りをしてきました。数年後、PC雑誌から離れてからは、ゲームを作ることに関わることがなくなって、会社勤めのサラリーマン生活を送っていましたが、フリーになってからまとまった趣味の時間が取れるようになってきたときに見つけたUnityを使って、ゲーム作りを再開したという流れです。 Daedalus Machine これまでにいくつのゲームを作ってこられましたか。またそれらのゲームについて教えていただけますか。 Hamazaki Factory PCで作ったものは記憶も現物も不明瞭(雑誌には掲載されたので残ってないことはないですが、手元にあるかどうかも不明)なので、リリースしたアプリを紹介していきます。ただ、どのアプリもほとんど動きがなく、死にアプリと化していますが……。 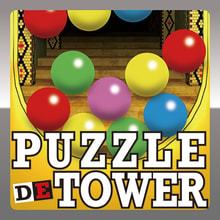
Puzzle De Tower (Amazonアプリストア) Unityを使って初めて作ったアプリです。色の同じ球を合わせて消していく、落ち物パズルゲーム。キャラモデルに挑戦したりと欲張った記憶があります。半年くらいかかったかなぁ。 

vs係長 (Google Play) 背後から来る敵を打ち倒すCardBoardを使ったVRっぽいシューティング(?)ゲームです。下の「夏恋」を作っている最中に気分転換で作ったものです。これもVoxelエディタを使ったりして、2週間くらいで適当に作った作品です。 
夏恋 karen 〝好き〟から始まる物語 (Google Play) スマホで縦書きのテキストビューアーが作ってみたくて始めたら、なぜかこんなゲームになったというもの。
これまでシナリオなんて書いたことないし、キャライラストだってはるか昔に趣味で書いたことがあるのに、なんでやろうと思ったのか、最後まで突き進めたのかいまだに不思議だったりします(実際に何度か心折れて中断してましたけど)。トータルで9カ月くらいかかった作品です。 関連コンテンツ
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
|
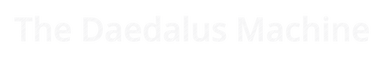


 RSS Feed
RSS Feed