|
7/11/2017 0 Comments Pon Pon Gamesとインタビュー 第2部
Pon Pon Gamesとのインタビュー、第2部
シュールズ・ダグラス (Douglas SCHULES)によるインタビュー
Daedalus Machine
以前、私たちが話した時には、Pon Pon Gamesのメンバーは浜野様のみとおっしゃいました。一人では、ゲームを作るのは大変そうですが、どのぐらいかかりましたか。 Pon Pon Games どこからどこまでを『ヒーラーは二度死ぬ』の制作期間とするか、非常に悩ましいのですが、概ね次の通りです。
DM 新しいゲーム作成者はゲームを作成する期間についてはあまり考えない事かと思います。このゲームについてどんな事を加えたかったか、もしくは加えたかったけど入れられなかった事などありましたら教えていただけますか。最初に自分が考えていたものと比べて、ゲームプレイのメカニックスやできる事が最終的に違った物はありますか。 PPG ポケットモンスターのポケモンずかんのように、出会った敵キャラの姿や能力を閲覧できる、「エネミー図鑑」のようなものを入れたかったです。 当初は、終わりが無く死ぬまで経験値(=スコア)を稼ぐだけのいわゆるEndless-Runタイプのゲームとして作りはじめました。また、色違いのスライムしか登場せず、『ぷよぷよ』のようにその並び方に応じてスライムが特殊な技を使ってくるようなアイデアがありました。(プロトタイプの画像を添付しました。左上の経験値がスコアの代わりです)。 DM ゲーム作成に興味のある人にどうするのがお薦めと言えますか。 PPG 今はゲーム制作の敷居も、それを公開する敷居も下がっているので、ツールでまずは小さなゲームを作ってSNS等で発信してみるといいと思います。GameMaker:Studioは取っつきがよく、またゲーム作りの普遍的なテクニックも身に付くと聞いています。(私は使ったことが無いですが。)ゲームジャムに参加するのも、情報や繋がりを得るいい機会だと思います。 DM マーケティングについてはどんな問題や困難がありましたか。 PPG 基本的にマーケティングについてはプロフェッショナルである両パブリッシャーさん(アクティブゲーミングメディアさんとメディアスケープさん)にほぼお任せしております。私自身は、東京ゲームショウ、デジゲー博、Busan Indie ConnectやTaipei Game Showといった国内外のイベントへ出来る限り参加し、露出を増やすことにしています。お客様の目に直接触れるだけでなく、メディアやブログ等で紹介していただけることもあるので、セールスに効果的なのではないかと期待しています。 DM 多くの日本のディベロッパーが海外で自分の作品を売りたいと思っているように、浜野様もプレイズムさんを使っています。彼らは実際どのような事をしてくれるのでしょうか。 PPG ディベロッパーやタイトルによって必要なサポートは変わってくると思いますが、 一般的には次のようなところではないでしょうか。
DM 今日のマーケットで成功するためには、インディディベロッパーは自分達の作品を複数のプラットフォームに出す必要があります。ディベロッパー目線で、こういった様々なプラットフォームを管理するのは難しいですか。 PPG UnityやUnreal Engineのような、マルチプラットフォームに対応したゲームエンジンのおかげで、以前よりは技術的な障壁は低くなっているようです。しかし依然として、特性のまったく異なるプラットフォームを両方ターゲットとする場合は、同時開発は困難なように思います。 【例】
DM ゲームの言語は日本語と英語が付いています。私が話した多くのゲームクリエーターはローカリゼーションをサポートするPlayismのようなサービスを使っているそうです。Pon Pon Gamesも同じような戦略でしたか。 PPG かかる費用やゲームの修正時のフットワークを考慮し、また、幸い文章量があまり多くないゲームなので、『ヒーラーは二度死ぬ』では翻訳そのものは自分で行うことにしました。まずは私自身で英語に翻訳し、その英文をアメリカのWolfgameさんに添削していただいています。一方、Steamのストアにおける紹介文など、ゲーム外のテキストはPlayismさんにすべてお任せしています。また、Playismさんのスタッフにご指摘いただいて修正したゲーム中の英文も数か所あります。 DM 東京のインディーズゲーム界について説明していただけますか。 PPG 私の目に見えている範囲でしかお話できないのですが、日本の「インディーゲーム」界には概ね次のような人たちがいると思っています。(もちろん、互いにある程度オーバーラップしていますし、近年境目も曖昧になりつつあります。)
東京近郊の展示イベントとしては、東京ゲームショウ、コミックマーケット、デジゲー博、ニコニコ闘会議、Tokyo Indie Fes、Indie Stream Fes、博麗神社例大祭、東京ロケテゲームショウ等があります。 東京近郊のコミュニティイベントは、Tokyo IndiesやPicotachi、Hotline Tokyo等があります。 DM これらのインディ関連イベントで、日本でゲームを作っている人にお薦めのイベントはありますか? PPG Tokyo Indiesに行くと、インターネットでは得られない様々な情報を聞けて、また他の制作者から刺激をもらえるので、非常に有効ではないでしょうか。
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
|
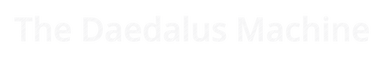


 RSS Feed
RSS Feed