|
ゲーム影響、Steam、ゲーム開発の難しさについて話します
Daedalus Machine
まず御サークルについて簡単に教えていただけますか。例えば、活動期間やこれまで作成されたゲームの数など。 Primary Orbit 個人サークル「PrimaryOrbit」は、石黒しなの1名の個人サークルです。 活動は2015年からで処女作「メルヘンフォーレスト~メルンちゃんと森の贈り物~」の追加開発のみを行っています。作りたいものは山ほどあるのですが、現状は上記以外をやる時間的余裕がないという状態でもあります。 Daedalus Machine 「Primary Orbit」という名前はどうやって決めましたか。 Primary Orbit サークルの活動がゆくゆくは大きくなって、自身の生活における主要な活動になるところまで成長できたら嬉しいなという願いを込めて、そのような名前になっています。 Daedalus Machine 「メルヘンフォーレスト」本体と追加コンテンツのストーリーやゲームプレイを簡単に説明していただけますか。 Primary Orbit 「メルヘンフォーレスト」は、フル3Dで描かれるファンタジー世界の小さな森にすむ薬屋さんの女の子「メルンちゃん」を操作して、一人前の薬師をめざすアドベンチャーRPGです。ストーリーは2部構成になっていて、第1部では一人前の薬師になるのを目標に、森の住人たちの悩みなんかを解決しながら薬の素材を集めるのが主な内容です。第2部は、行方不明の母親を探して森の地下遺跡を冒険するダンジョン探索型RPGへと内容・システムがガラリと変わっていきます。 追加コンテンツ「星幽界の鎮魂歌」は、第2部(ダンジョン)のシステムを拡張した内容となっており、第2部で挑んだ地下遺跡のさらに深い世界を冒険します。ここでは主に第2部で出会ったキャラクター達の過去が語られていきます。 Daedalus Machine 第一部のゲームプレイの部分は「アトリエシリーズ」に似ていると思います。その影響といえますか。 Primary Orbit はい、受けています。ただ、アトリエシリーズのように調合システムをメインとしたゲーム性ではないのであくまで雰囲気程度です。 Daedalus Machine ゲームシステムを変える、特に途中で変えるのは多くの労力が必要のような気がします。なぜ第二部と追加コンテンツでシステムを変えたのでしょうか。 Primary Orbit 単純に勉強をしながら作業をしているので、自然と作れる物の幅が増えていった為です。 もともと、今作は習作程度で終わるつもりで開発スタートをした経緯もあり、前半部分は今見ると不満だらけですね。 Daedalus Machine その不満についてもう一度デザインしなおす予定はありますか。 Primary Orbit リリース後も継続的に修正は行ってきたのですが、大幅に作り直したバージョンがまさに本日上がりました。(笑) まずはsteamにてDL販売を開始いたします! Daedalus Machine ゲームコンセプトはどうやって思いつきましたか。 Primary Orbit エンディングがなくひたすらキャラクターや武器の強化をし続けるタイプのソシャゲが主流のスマホ界ですが、スマホでももっと家庭用ゲーム機のようなゲーム体験ができたらいいのにな、と思ったのが開発のスタートだったように思います。つまり、コンセプトは「家庭用ゲーム機のようなスマホゲーム」です。 Daedalus Machine まずゲームのメカニズムを先に考えてからストーリーを決められたのですね。一つのゲーム内に異なるタイプのゲームプレイスタイルを取り入れられたというのも理解できます。では、全体のストーリーやキャラクターはどうやって思いつきましたか。 Primary Orbit 昔に一人で描いていた漫画などからキャラクターを引っ張ってきています。(その漫画は本当に趣味で描いていたものなので特に公開等はしていません)漫画やゲーム・アニメ・漫画など自分が特に好きなものを詰め込んだような、そんな漫画でした。 ストーリーは後付けで、ゲームを実際に作りながらその場その場で考えていきましたが、自分が作品を通して言いたいこととか、そういったメッセージ性はぶれない様に気を付けました。 Daedalus Machine 「メルヘンフォーレスト」のプレイヤーにどんな体験をしてほしいと考えていますか。 Primary Orbit 昔は家庭用ゲーム機でよく遊んでいたけど、最近はスマホゲームしかやらなくなっちゃったなんて人が結構いるんじゃないかと思うのですが、また家庭用ゲーム機に夢中になった「あの頃」の気持ちを思い出してほしいと思いながら作っています。「あの頃の気持ち」とは人によって様々で、ファミリーコンピューター時代の「説明不足で不条理な難関」を命からがら乗り越えた時の達成感だったり、ゲームの世界観に引き込まれて夢中になって遊んだ経験だったり、ゲームから人生観のようなものを学びとったり。 プレイを終えた時に「久しぶりに家庭用ゲーム機で遊んでみようかな」と思ってもらえればそれが一番嬉しいです。 Daedalus Machine C93で「メルヘンフォーレスト」のPC版を買いましたが、デジゲー博2016でもPrimary Orbitのモバゲーもあったと思います。そのゲームについて教えていただけますか。PC版とどう違いますか。 Primary Orbit スマホ版の開発が最初で、それをPCへ移植したという経緯がございますので、基本的な内容はPCもスマホも同じですが、PC版は映像面の強化を継続的に行っています。 拡張パック「星幽界の鎮魂歌」は現時点でPCのパッケージ版のみのリリースとなっています。 ※steam販売がまもなく開始されるのですが、そちらでは「星幽界の鎮魂歌」はすぐにリリースされることはないと思います。なぜなら、こちらは翻訳を全く進めていない為です。 Daedalus Machine 「メルヘンフォーレスト」はSteamでリリースされるという事ですが、多くの日本人デベロッパーはPlayismのようなパブリッシャーを使って自分達のゲームを翻訳し、リリースしています。Steamにどうやってリリースされましたか。 Primary Orbit スマホ版を日本語のみでリリースした際に、ゲームを遊んでくださった韓国と台湾の方から、翻訳を手伝いたいとありがたい申し出がありましたので、有志でご協力をいただき韓国語と繁体字の対応ができました。その後、イベントでお声がけいただいたパブリッシャーから英語版の翻訳データもご提供いただき今日に至ります。 当初パブリッシャーからSteam版をリリースしてもらう予定だったのですが、そこが合同会社であったため、日本からではパブリッシングができないことが後から分かりまして、結局、私個人で開発者アカウントの登録を行い、個人でのリリースとなりました。 Daedalus Machine Steamでゲームをリリースするプロセスについて教えていただけますか。他の日本のインディデベロッパーが知っておくと良い情報はありますか。 Primary Orbit SteamWorksのナビゲーションにしたがえば大抵は理解できると思いますが、つまずいたのは税金の申請(租税条約)でした。米税務署にITIN取得の申請をしなければならないと勘違いをしまして、パスポートを取りに行ったり、米税務署に手紙を書いたりと色々苦労したのですが、最終的にはこの手続きは不要で、SteamWorksのTIN入力画面で日本のマイナンバーを入力すればクリアできました。 マイナンバーがTINに該当するなんて知らなかったので驚きました。 Daedalus Machine 家庭用ゲーム機のようなスマホゲームを作るためにデザインやストーリーについて何をしましたか。PCとスマホでインターフェースが異なりますが、それらのプラットフォームにそのアイデアを実装させる時にどういった事が難しいと感じましたか、またそれをどう解決されましたか。 Primary Orbit ファミコン時代~PS1くらいまでのドラクエとかFFなど好きだった作品を改めてプレイしたり、プレイ動画を見て、良いところも悪いところも含めて、参考にしています。 色々見直してみると、設定はあるけど多くは語らないセリフがシンプルで良いな、と感じそれらを取り入れた・・・はずなんですが、セリフ多いところは多いですね・・・。 それから、クリア後に来る達成感と、ゲームが1本終わっちゃった事を残念にも思う気持ちと、でも何かに満たされたような謎の放心状態、なんか上手く言えないんですけど、自分が過去に経験した「そういうもの」がプレイ後の残るようにしたつもりですが、それが上手くいったかどうかは分からないですが、何年かしても記憶の片隅に残れるゲームになれると嬉しいなという思いで作っています。 スマホからPCへ移植したので、コントローラーの対応が知見がなくて苦労しました (そもそもシステム面は特に全て知見がない状態で作っていますが、、、)。解決方法はunityのassetに頼れる部分は極力頼って逃げました。個人的にPC移植での苦労より、機種数が多いAndroid対応が匙を投げたいくらいめんどくさいなと思いました・・・。ごまんとある機種を一人では検証しきれないですね。 関連コンテンツ
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
|
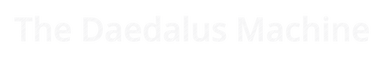
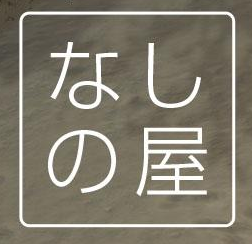
 RSS Feed
RSS Feed